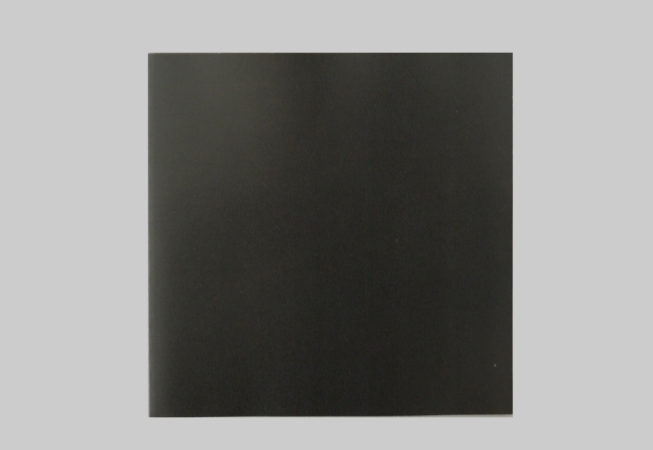あのね、と絶えず問いかけずにはいられない、肉親の追憶と記憶の物語。
写真から音が聞こえてくる。決して大きな音ではないけれど、絶えず聞こえてくる日々のささやき。
日常のささやかな積み重ねが層になり、多重奏となって私たちの耳に響く。
誰もが持っている、その人の音。
——————————————–
令和二年、早春。遠縁を訪ねた先で季節はずれの大雪に見舞われた。
雪国育ちの彼女は、冬になれば雪の降る音に包まれて暮らしてきたのだろう。
積雪に折れた桜の枝をひろい水にさす。翌朝見ると、つぼみが開いていた。
面会は叶なず彼女に花を見せることはできなかったが、外からほのかに差し込む雪の明かりに写真を撮った。
後に彼女は彼女は九十九歳でこの世を去った。
あの白い朝を思い出す。冬になれば雪の音が、春になれば花の咲く音さえ彼女の耳に届いていたのでは、と他愛もないことを考える。それらがたとえ人には聞こえないものだとしても、心根に静かに語りかけてくれていただろう。
私にもそのような音があるだろうか。自らを準えるうちに脳裏への響きが経験の歯車をすり合わせる。
過日の光景がいくつも描かれていき、これまでの半生をたどる旅になっていく。思い出す人があり、日々がある。
傍らに寄り添う者たちの声に耳を澄ましながら、今日もひとり歩いていく。
21×21cm、48p 3,300円